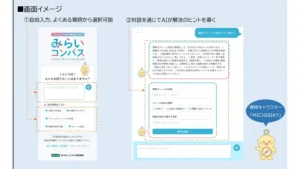警察庁とみずほ・三菱UFJなど8都銀が情報連携協定 SNS投資詐欺撲滅へ口座情報共有
警察庁組織犯罪対策第二課は18日、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそなグループ4行、三井住友信託銀行の計8行と、特殊詐欺等の被害防止を目的とする「情報連携協定書」を締結した。協定の柱は、各行が日常的に実施する取引モニタリングで「詐欺被害に遭っている可能性が高い」と判断した口座や送金に関する情報を、関係する都道府県警および警察庁へ迅速に提供する仕組みである。警察は提供を受けた情報を基に捜査に着手し、被害の未然防止や犯人グループの摘発につなげる。
背景には、2024年(令和6年)の特殊詐欺被害額が統計開始以降で最悪水準になった現状がある。特にSNS型投資詐欺やロマンス詐欺は前年の約3倍に急増し、高齢者だけでなく若年層にも被害が広がっている。こうした情勢を受け、警察庁と金融庁は昨年8月、全国の金融機関に対し「預貯金口座の不正利用防止策の強化」を連名で要請。その中で警察への情報提供体制の構築を求めていた。
今回の協定はこの要請を具体化するもので、都市銀行が一斉に参加するのは初めて。協定金融機関は独自のAIやルールベースのシステムで不審取引を検知し、疑わしいケースを整理したうえで警察へ連絡する。従来は個別案件ごとに照会・回答を行うため時間を要していたが、新協定により一元的でスピーディーな情報共有が可能になる。警察庁は「送金停止や口座凍結を迅速に行えることで二次被害の防止に大きな効果が期待できる」としている。
警察庁は今年1月にゆうちょ銀行、2月にPayPay銀行とも同様の協定を締結済みで、今回の8行追加で連携網は11行へ拡大した。今後は地方銀行や信用金庫との協定も視野に入れ、全国レベルでの情報連携体制を整備する方針だ。金融機関側も「顧客資産を守る社会的責任の一環として協力を強化する」としており、店舗やオンラインバンキングでの注意喚起、コールセンターでの声掛けなど多面的な対策を進める。
警察庁は協定の運用状況を定期的に検証し、共有フォーマットの標準化やデジタル化も推進する考えである。SNSを悪用した巧妙な詐欺が増える中、官民が垣根を越えて迅速に情報を結び付ける今回の枠組みが、被害抑止のカギとなりそうだ。
添付画像一覧